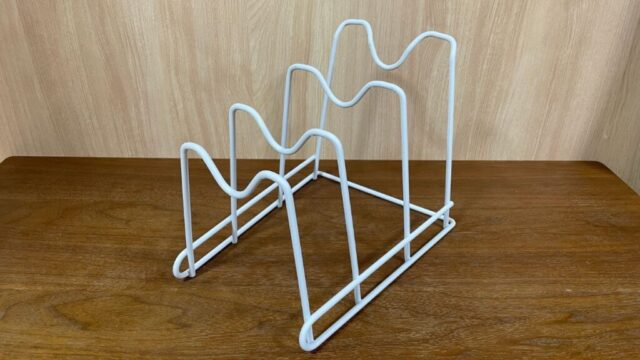実家の片付けがなかなか進まなくて困っている。
実家は安心できる場所である一方で、散らかりが気になる方も少なくないのではないでしょうか?ライフステージの変化とともに考えたい実家の整理整頓。今だからできることを家族と話し合って進めたいものです。
- 家族が安心できる快適な空間作り
- 部屋の有効活用(子どもや孫部屋)
- 先を見越した整理(生前整理)
こんにちは。さく(@SakuBase78)です。整理整頓が好きなシンプリストです。
検索の手間を減らし「解決したい!」に役立つサイトを運営しています。
私も数年間、絶賛実家の片付け中です。それでも必須なタスクではないので、それぞれの価値観を大事にした上で進めましょう。
年末の大掃除や実家に顔を出せる時などに合わせて、ぜひ参考にしてみてください。
- 状態やオーダーによっては片付けに100万円かかることもある
- モノや片付けの価値観の違いは受け入れる
- 小さな目標から少しずつ
- データ化の活用
- 片付け専門業者費用を知っておく
はじめに
片付けられた実家のモノ
子どもの頃も「〇〇が欲しい」「〇〇がしてみたい」を叶えてくれた両親。感謝の気持ちでいっぱいです。
子どもたちが社会人になり、子ども部屋の使い方が変わってくると、お世話になった家具も手放しても良い時が来ます。
実家で片付けることができた大きめのものはこちらです。
- 二段ベット 1つ
- 勉強机、椅子セット 2つ
- タンス 2つ
- ソファー 1つ
- ブラウン管テレビ 2つ
- パソコン用マルチ机と椅子 1つ
- お雛様 大型
- 各パソコン類や家電類 複数
- 衣類、食器類
- 書類等
処分するにもお金がかかるものが多いです。また、引き取り手が見つからなかったり、引き取ってもらえなかったりで、解体作業もしました。
お雛様は供養の方法をとりました。ざっとにはなりましたが、1つずつの処分方法も異なりました。
スペースができたおかげで、取り入れられることも増えています。
片付けに100万円かかることもある
間取りや作業量にもよるものの、片付け専門業者に頼む必要があるほどの規模になってくると、費用も増していきます。
自分たちでできる範囲のところは、進めておけると大事にしているものがわかったり、万が一の際の対応がスムーズになります。
家族が対応することになると思うので、大事なことは早めに話し合えるといいですね。
性格や価値観に違いがあることを受け止める
家族の数だけ、家族のカタチがあります。「好きなこと・嫌なこと」「得意・苦手」は、家族でも違いがあって当たり前です。
お互いに気持ちよく安心・安全に暮らすために、その家族のルールの中でマナーを守りながら生活していますが、「自分・家の常識が他人の非常識」になっているケースもあるのかもしれません。
片付けやモノに対する考え方も「モノに執着しやすい人」「経験や見えないモノを大切にする人」など様々です。
昔ながらの根付いた価値観を大人になってから変えることはとても大変ですが、性格や価値観の違いを受け止めた上で、何ならできそうかを考えて話し合うことは大切な過程です。
多様な価値観を認めつつ、相手を尊重した思いやりのある言動を心掛けたいですね。
片付けも「気持ちよく暮らせる方法」「将来的に必要になる整理」に向けて、家族で協力して取り組んでみてはいかがでしょうか?
同じ方向を向けているか
度を越えた「ゴミ屋敷」「潔癖」を押し付けることはあまり好まれませんが、程よい住環境を目指したいものです。
「整理整頓されている・散らかっている」の基準は、人それぞれであいまいな部分もあります。
片付いている状態を維持するための行動はシンプルです。
- 使う分・必要な分だけ買う
使ったものは片付ける
役目を終えたものは手放す
「当たり前のことを当たり前にやる」ことは、何事においても初心で近道ですね。
さて、家族全員が「きれい好き」「散らかりが気にならない」場合には、その家族にとっての当たり前が一致しているとトラブルは起きにくいですが、認識の差によって社会では苦労することが多くなりそうです。
良い習慣は取り入れていけるといいですね。
進め方
片付けるメリットを伝えて理解してもらう
人は変化を好みませんが、変化後のことが想像できたり、体験して気付けたりすることで新しい考え方を取り入れやすくなります。
実家に住んでいない期間が長い場合には、実家の使い方に口を出しにくいこともあります。
住んでいる人にとっても、家族が帰ってきたときにも安心してくつろげる空間でありたい!
そのためには、「片付けるべき」を押し付けるのではなく、片付けることで得られるメリットを説明して受け入れてもらえるように伝えてみましょう。
筆者もよく陥るのですが、「説明して伝えた」と「相手が理解できた」は別物です。
誤解がある場合には、説明に食い違いがあったままになり関係がこじれる原因にもなります。
「話し手の説明力」と「聞き手の理解力」に応じて、相手に合う話し方や聞いて意図をくめる力をつけて、なるべく正しく意図や本質の理解を深めていきたいものです。
「やってみてもいっか」と思える行動につながりやすいです。
相手を変えることはたくさんの労力を使うため、小さなことから協力し合えるようになりたいものです。
元気なうちに整理整頓ができると、日々の暮らしの気持ち良さに加えて、万が一の時の整理もしやすくなります。
片付ける費用が抑えられたり、必要なモノが見て分かりやすかったりと、後から使う労力を減らすことができますよ。

小さな目標を立てて、できそうなことから協力してもらう
短期集中型で進められるとはかどるのですが、複数の人が関わる場合には段取りが大事です。無理に進めると、もめる原因になってしまうからです。
予定を合わせて時間を決めたり、使う使わないを一緒に見てくれるかを依頼したりするなど、相手ができそうなことから進めてみましょう。
「いつまで」「どのくらい」「どのスペース」を進めたいと、期限を決めるとお互いに意識もしやすくなります。
お金をかけてでも業者に頼むことも検討
遠方であったり、毎回片付けのために実家へいったりも今を大切にできていない気もします。
モノで溢れていて万が一の時に大変そうと感じるなら、今のうちから費用についても家族で話しておきましょう。
成人した「子ども」任せではなく、家族のことを考えるなら、人の手を借りるときのことを考えた話し合いができると円滑ですね。
昔ながらの考えも大事!だけど、お互い様の気持ちで思いやれるともっといいですね。
自分たちだけでやろうとしても無理も出てくる時は、相場を知った上で、プロに頼む方法も検討してみましょう。
トラブルを避けるための心得
共有スペースと個人スペースを分けて考える
衛生観念が近い人との暮らしは、居心地が良い空間を作りやすいです。スッキリした空間での暮らしは気持ち良くて活動のパフォーマンスが上がります。
さて、「安心で安全な暮らし」「思いやりのある社会づくり」のために、ルール・マナー・モラルがあります。
性格や価値観に違いがあることを受け止めた上で、家の中の共有する場所の使い方はともに認識し合ってみんなで気持ちよく使いたいですね。
共有スペースには、「玄関・リビング・ダイニング・キッチン・洗面所・お風呂・トイレ・収納スペース・庭や敷地」などがあります。
一方で、個人スペースには、「自分の部屋・割り当てられた収納スペース」などがあります。
自分にとってのゴミと他の人にとってのゴミは違います。
筆者も何度か共有スペースのモノを誤って処分してしまい不快な思いをさせたことがあります。
改めて聞くことで防げたかもしれませんし、きちんと整理して分かるように個人スペースに持っていくなどすれば防げたかもしれません。
どちらにも改善点はあったのだと反省しています。
同じことを繰り返さないためにも、相手の立場で考えて学んでいくようにしましょう。

捨てるか悩んだ時点で必要ではない
モノを捨てられない方が考えがちな、「いつか使うかもしれない」「もったいない」は、都合のいい思い込みであるケースがほとんどです。
「いつか使う」は、ほぼ使わないですし、「もったいない」は、捨てる行為についてだけの言葉で実際に使っていなければもったいない行動を日々していることになります。
「いる・いらない」ではなく「使う・使わない」で決めて、考え方を上手く上書きしてみましょう。
修理して使うも良し、新しいモノを取り入れて今あるものを手放すも良し。
もちろん、手放したくないモノを無理に手放す必要はありませんよ。
モノに埋もれる暮らしからは卒業して、自分で選んで整えていける暮らしを手に入れていきませんか?

思い入れのあるものへの感謝・データ化
思い入れのある「プレゼント・制作物・写真」は、手放しづらいですよね。
モノだけに価値を置くと捨てにくくなりますが、くれた人のその時の気持ちに改めて感謝したり、写真にしてデータ化したり、小さいアルバムに入れ直してコンパクトにしたりと、気持ちよく手放せる方法を取り入れてみましょう。
実物はなくなりますが、写真にすると後から見て懐かしむこともできますよ。膨大なデータをそのままにしておくと整理が大変になるため、定期的にデータを見直して整理しておくこともオススメします。
まとめ
実家の片付けには家族と話し合うことが一番大切だと感じています。片付くことと「片付く習慣が身に付く」「きれい好きになる」は、別物と考えておきましょう。
- 状態やオーダーによっては片付けに100万円かかることもある
- モノや片付けの価値観の違いは受け入れる
- 小さな目標から少しずつ
- データ化の活用
- 片付け専門業者費用を知っておく
自分の判断だけで片付けが進められない歯がゆさもありますが、空間がスッキリする喜びをみんなで分かち合ってよりよい暮らしになるように、コミニュケーションや考え方も整理していけるといいですね。
生前整理や遺品整理でかかる費用などを知って、納得した中で実家の片付けが進むといいですね。